愛用の自転車が突然なくなり、「盗まれたかもしれない」と気づいた時、誰もが冷静ではいられなくなるものです。
特に、防犯登録をしたものの「番号がわからない」という状況では、どうすれば良いのか途方に暮れてしまう方も多いのではないでしょうか。
しかし、心配は無用です。
この記事では、防犯登録番号がわからなくても、落ち着いて対処できる具体的な方法を、初めての方にもわかりやすく解説します。
盗難届の提出から、二度と同じ経験を繰り返さないための対策まで、順を追って見ていきましょう。
自転車を盗まれたら、まずやるべき初期行動

自転車ライフナビ・イメージ
自転車が見当たらないと気づいたら、まずはパニックにならずに冷静になることが大切です。
焦って行動する前に、一つひとつ状況を確認していくことで、単なる思い違いであったり、その後の手続きをスムーズに進められたりします。
落ち着いて盗難場所と状況を再確認
まずは、本当に盗難なのかどうかを確かめましょう。
最後に自転車を停めた場所や日時を、もう一度正確に思い出してみてください。
記憶が曖昧で、いつもとは違う場所に停めていたという可能性も考えられます。
駐輪場の別の階や、少し離れた場所に移動させられていないか、周辺をよく確認することが重要です。
自転車の色やメーカーなど特徴をメモする
盗難届を提出する際には、自転車の特徴をできるだけ詳しく伝える必要があります。
後で慌てないように、覚えているうちにスマートフォンのメモ機能や紙に書き出しておきましょう。
以下の項目を参考に、具体的にリストアップしてみてください。
自転車の情報の例
- メーカー名と車種名(例:ブリヂストン、アルベルト)
- 色やデザイン(例:シルバー、フレームに青いライン)
- 車体の種類(例:シティサイクル、電動アシスト自転車、クロスバイク)
- カゴや荷台の有無、色、素材
- 貼っているステッカーやシール
- サドルの特徴(例:色、破れ)
- その他、傷や凹みなど個別の目印
自分の行動範囲や駐輪場所を探してみる
盗難と断定する前に、ご自身の行動を振り返ってみましょう。
その日に立ち寄ったお店や友人の家など、普段とは違う場所に停めた可能性はないでしょうか。
また、大規模な商業施設や駅の駐輪場では、管理人が移動させているケースもあります。
心当たりのある場所をもう一度探し、管理事務所などにも問い合わせてみることをお勧めします。
防犯登録番号がわからない時の確認方法
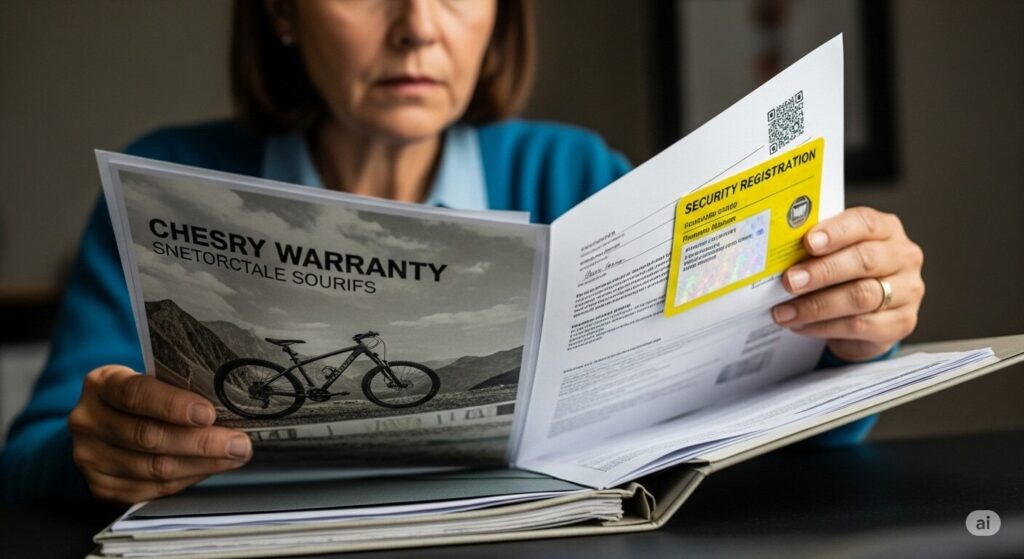
自転車ライフナビ・イメージ
いざ盗難届を出そうと思っても、防犯登録番号がわからないと手続きができないのでは、と不安になりますよね。
しかし、番号を確認する方法はいくつかありますので、諦める必要はありません。
防犯登録カード(お客様控)が手元にないか探す
自転車を購入した際に、防犯登録をすると「防犯登録カード(お客様控)」という黄色い紙などの控えが渡されます。
多くの場合、自転車の保証書や取扱説明書と一緒に保管されています。
まずは書類を保管しているファイルや引き出しの中をくまなく探してみてください。
このカードがあれば、防犯登録番号がすぐにわかります。
購入した自転車販売店への問い合わせ手順
防犯登録カードが見つからない場合は、自転車を購入した販売店に問い合わせてみましょう。
販売店では、購入者のデータとして防犯登録の情報を保管していることがほとんどです。
電話などで問い合わせる際は、以下の情報を伝えるとスムーズです。
- 自転車を購入したおおよその時期
- 購入者の氏名と連絡先
- 購入した自転車のメーカーや車種、色などの特徴
これらの情報をもとに、販売店側で防犯登録番号を調べてもらえる可能性があります。
車体番号の確認方法と記載場所
防犯登録カードもなく、購入したお店もわからない、または閉店してしまったという場合に頼りになるのが「車体番号」です。
車体番号は、自転車一台一台に割り振られた固有の番号で、フレームに刻印されています。
防犯登録の情報は、この車体番号と紐づけられています。
警察に盗難届を出す際、防犯登録番号がわからなくても、この車体番号がわかれば照会が可能です。
車体番号の主な記載場所
- ハンドルの根元(ヘッドチューブ)
- ペダルを漕ぐ部分の裏側(ボトムブラケット)
- サドル下のフレーム部分(シートチューブ)
自転車をひっくり返したり、ライトで照らしたりして確認してみてください。
番号不明でも大丈夫!盗難届の提出ステップ

自転車ライフナビ・イメージ
自転車の特徴をメモし、防犯登録番号や車体番号を確認しようと試みたら、いよいよ警察へ盗難届を提出します。
たとえ番号がどちらも不明なままでも、盗難届は受理されますので安心してください。
最寄りの交番や警察署で手続きする
盗難届は、盗まれた場所に関わらず、お近くの交番や警察署の窓口で提出できます。
「盗難届出書」という書類に、盗難にあった日時や場所、自転車の特徴、ご自身の住所・氏名などを記入します。
わからないことがあれば、その場で警察官が教えてくれるので、正直に伝えましょう。
盗難届の提出に必要な持ち物リスト
手続きを円滑に進めるために、以下の持ち物を準備していくと良いでしょう。
- 身分証明書(運転免許証、マイナンバーカード、健康保険証など)
- 印鑑(認印で可、自治体によっては不要な場合もあります)
- 自転車の特徴をまとめたメモ
- (あれば)防犯登録カードや保証書
- (わかれば)防犯登録番号や車体番号の控え
すべてが揃っていなくても届け出は可能ですが、情報が多いほど発見される可能性が高まります。
届け出はネットや電話でできる?
「警察署に行く時間がない」という場合、ネットや電話で手続きができないか考えるかもしれません。
しかし、2025年7月現在、多くの自治体では盗難届の正式な受理は、警察署や交番での対面による手続きが原則となっています。
これは、本人確認や盗難状況の詳しい聞き取りを確実に行うためです。
一部の地域では電子申請システムを導入している場合もありますが、まずは最寄りの警察署に電話で確認してみるのが確実です。
盗難届を提出した後の流れと注意点

自転車ライフナビ・イメージ
無事に盗難届を提出した後も、いくつか知っておくべきことや、ご自身で確認できることがあります。
発見の連絡を待つ間の注意点をまとめました。
発行される受理番号は必ず保管する
盗難届を提出すると、「受理番号」が発行されます。
この番号は、届け出が正式に受理されたことを証明する大切な番号です。
後日、捜査状況を問い合わせたり、自転車が見つかって引き取りに行ったりする際に必要となります。
受理番号が記載された控えの書類は、絶対になくさないように大切に保管しておきましょう。
自転車が見つかった場合の警察からの連絡
盗難届が出された自転車が発見されると、警察のデータベースと照合されます。
あなたの自転車だと確認された場合、届け出の際に記載した連絡先に警察から電話などで連絡が入ります。
その後、指定された警察署や保管場所へ自転車を引き取りに行く流れとなります。
放置自転車として回収されていないか確認する方法
盗難ではなく、駅前などに長時間放置されたことで「放置自転車」として自治体に回収されているケースも少なくありません。
盗難届を提出した後も、念のためお住まいの市区町村の担当部署(環境課や道路管理課など)に問い合わせてみましょう。
自治体のホームページで、回収した自転車の情報を公開している場合もあります。
その際は、撤去された場所や日時、自転車の特徴から自分のものがないか確認できます。
二度と繰り返さないための盗難防止策

自転車ライフナビ・イメージ
一度でも盗難にあうと、その悔しさや手続きの手間は二度と経験したくないものです。
自転車が戻ってきても、また戻ってこなくても、今後のために万全の盗難対策を心がけましょう。
地球ロックなど効果的な鍵のかけ方
自転車の盗難を防ぐ最も基本的な対策は、鍵のかけ方を工夫することです。
備え付けの鍵だけでなく、ワイヤーロックやU字ロックなどの補助錠を追加して「ダブルロック」にすることが非常に効果的です。
さらに、「地球ロック」と呼ばれる、ガードレールや支柱など、地面に固定された動かせない物と自転車のフレームを一緒にロックする方法を取り入れると、盗難のリスクを大幅に減らすことができます。
自転車保険に加入するメリットとは
万が一の事態に備えて、自転車保険への加入を検討するのも一つの手です。
多くの自転車保険には、事故の際の賠償責任補償だけでなく、盗難補償が付帯しているプランがあります。
保険に加入していれば、自転車が盗まれて見つからなかった場合に、新しい自転車の購入費用の一部が補償されるなど、金銭的な負担を軽減することができます。
防犯登録情報の更新・抹消の重要性
防犯登録は、登録した時点での情報が記録されています。
そのため、引っ越しで住所が変わったり、自転車を誰かに譲ったりした場合は、必ず情報の変更手続きが必要です。
また、自転車を処分する際には、登録の抹消手続きを行いましょう。
これらの手続きを怠ると、万が一の際に本人確認が遅れたり、次の所有者がトラブルに巻き込まれたりする原因にもなります。
まとめ:防犯登録番号がわからなくても盗難届は出せる

自転車ライフナビ・イメージ
大切な自転車が盗まれた時、防犯登録番号がわからないという状況は、非常に心細く感じるものです。
しかし、この記事で解説したように、番号が不明なままでも盗難届を提出することは可能です。
まずは落ち着いて自転車の特徴を思い出し、身分証明書を持って最寄りの交番や警察署へ相談に行くことから始めましょう。
諦めずに一つひとつ行動することが、愛車を取り戻すための第一歩となります。
そして、今後は二度と悲しい思いをしないよう、日頃からの防犯対策を徹底することが何よりも大切です。
【関連記事】




